
2024年度の生保2大問の試験問題を解説します。
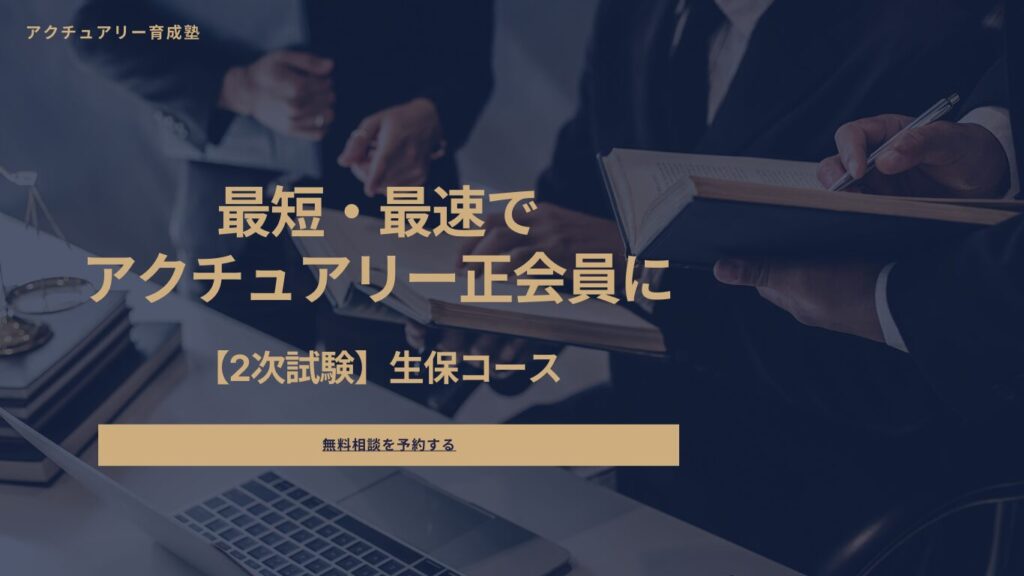
※本解答速報は、試験問題に対する参考解答を提供するものであり、公式解答ではありません。正確な解答は、日本アクチュアリー会が発表する公式情報をご確認ください。
本情報の作成には細心の注意を払っておりますが、誤りが含まれる可能性があります。本速報を利用することで生じるいかなる結果についても、当方は責任を負いかねます。
間違えている箇所がございましたら、コメントでご教示いただけますと幸いです。
問題については、日本アクチュアリー会のサイトから引用させていただいております。
https://www.actuaries.jp/examin/2024exam/20241213/2024-H-1213.pdf
3-1.契約者配当(3商品の比較)
問題
(1)契約者(社員)配当について、次の(ア)、(イ)の各問に答えなさい。(計25点)
(ア)契約者配当を行う理由を簡潔に説明しなさい。(解答の制限字数は1000字)(6点)(イ)あなたの所属会社では、次の3つの生命保険商品を販売している。
・一時払終身保険
・平準払終身保険
・平準払終身医療保険(無解約返戻金型)
いずれも毎年配当タイプ(毎年の利差配当、死差(危険差)配当、費差配当と消滅時特別配当がある保険契約)であり、利差益、死差(危険差)益、費差益は継続的に安定して得られている。また、平準払終身医療保険(無解約返戻金型)の解約実績は、予定解約率をやや上回り安定的に推移している。
なお、昨今の金利上昇に伴い、平準払終身保険は予定利率の引き上げを近年実施した。以上を踏まえ、公正・衡平な契約者配当のあり方について、アクチュアリーとして所見を述べなさい。なお、解答にあたっては次の観点を含めること。(解答の制限字数は3500字)(19点)
A.商品特性の相違を踏まえた留意点
B.平準払終身保険について、新旧予定利率契約に対する利差配当水準
C.キャピタルゲイン還元の考え方・留意点
解答
(ア)契約者配当を行う理由
(ア)
1. 安全性の原則
・保険料計算基礎に組み込んだ安全割増を、時間の経過とともに実際の経営諸効率が判明するにつれて、契約者配当として還元することで契約者間の公平性を保持
2. 経験料率の採用
・適切な保険事故発生率の測定が困難な場合の、真の保険事故発生率への保険料率の補正
3. 保険料率の調整
・保険料率を細分化することが事務的に負担になる場合の、保険料率の事後調整
4. 競争上の手段
・保険料率が行政監督上、ほとんど統一的に定められている場合の競争手段
5. 購買力の実質価値保全
・インフレによる保険契約上の給付の実質価値の保全
(イ)公正かつ衡平な契約者配当のあり方(3商品比較)
(イ)の所見部分については、筆者が必要と考える論点を列挙します。
アクチュアリー育成塾では、所見については、「書き始める前にアウトラインをまず書き出す。その後アウトラインに沿って文章を書いていく」方法で書くように指導しています。アウトラインが書けるかどうかが合否に直結してくるので、その練習を行うことが大切です!
一般論をどこまで書いて点がもらえるか不明ですが、過去問の模範解答をみても、一般論を書いている年もあるので、時間がある場合は書いた方がよいかと思います。ただし、時間がない場合は、聞かれている論点を重点的に書いた方が点をもらえると思います。
- 公正・公平な契約者配当を行う上では、『生命保険会社の保険計理人の実務基準』に規定されている次の公正・衡平な配当の要件を踏まえることが重要である。
- 責任準備金が適正に積み立てられ、かつ、会社の健全性維持のための必要額が準備されている状況において、配当所要額が決定されていること
- 配当の割当・分配が、個別契約の貢献に応じて行われていること
- 配当所要額の計算および配当の割当・分配が、適正な保険数理および一般に公正妥当と認められる企業会計の基準等に基づき、かつ、法令、通達の規定および保険約款の契約条項に則っていること
- 配当の割当・分配が、国民の死亡率の動向、市場金利の趨勢などから、保険契約者が期待するところを考慮したものであること
- また、公正かつ衡平な契約者配当の分配の際にも、次の原則を考慮することが必要である。
- ①公平性:商品内容、契約時期、保険金額、運用成果といった様々な要素に基づき計算された配当は、各契約者間の公平性が確保されているか。
- ②弾力性:利益の状況は毎年変化することが考えられるが、これに適応できる分配方法であるか。
- ③実務面の簡明性:収支への貢献度に応じて配当を行う場合、どの程度のレベルまで細分化したセグメントで行うか、どのような手法によるかは、事務負荷の点も考慮に入れるべき。
- ④契約者の理解:契約者に説明しやすく、理解されやすいものか。
- 払方の違い
- 一時払・平準払
- 給付内容の違い
- 死亡保険と医療保険
- 適切な区分経理
- 加入年齢層の違い
- 加入チャネルの違い(複数のチャネルで販売している場合)
- 通貨の違い(特に一時払は複数通貨の取扱いが考えられる)
- 平準払終身保険について、予定利率を引き上げ
- 調整配当と上乗せ配当
- 標準責任準備金制度の予定利率の遅効性による責任準備金の積立負担
- 今後の金利低下リスクも考慮
- 健全性の確保(セルフサポート)
- キャピタルゲインの具体例
- 債券の売却差損益
- 為替差損益
- 株式利益
- 不動産売却益
- 子会社売却益 等
- キャピタルゲインは中長期的に会社の利益およびソルベンシー確保への貢献に対して、契約者に還元すべきである
- その点では、消滅時特別配当に織り込むことが親和性があると考えられる
- 消滅契約に対する配当として、解約契約に支払うかどうかを考慮することも検討に値する。ただし、解約だろうと死亡だろうとで契約が消滅するまでの貢献度は変わらないので、そこで還元率に差を設けるのは公正かつ衡平かという論点がある
- 健全性には留意したうえで、還元水準は設定する
- 将来の金利動向や医療環境の変化なども考慮する
- キャピタルゲインは利差配当や消滅時特別配当に充てるべきであるが、危険差損や費差損の状況で支払うのは健全性の観点から好ましくない
- 利源別配当だけでなく、アセットシェアによる配当率の設定も必要
- 一時払
- MVAの有無によりキャピタルゲイン還元の考え方は大きく異なる
- 平準払
- 契約年度・経過年度別にキャピタルゲインの割当を行うことも考えられる
- 資産区分と商品区分の対応が重要である
解説
「契約者配当」の問題です。2019年問題3(1)やH26年、H20年と類似の問題なので、ちゃんと勉強していれば、書けた内容だと思います。
(ア)契約者配当を行う理由
過去でも頻出なので、落としたくないですね。ここで6点取れるかどうかは、合格に直結します。
最近の傾向では、大問3の各問題に(ア)(イ)など分割されており、前半部分(本問では(ア))で満点が取れるかどうかが合否を分けます。
もちろん、所見の中身も合格に影響しますが、「どこまで覚えられるかどうか」が合否に直結します。受験生のみなさまは、2次試験に受かるためには死ぬほど暗記が必要であると、心して勉強してほしいなと思います。
(イ)公正かつ衡平な契約者配当のあり方(3商品比較)
繰り返しになりますが、過去問で似たような問題が出ているので、だいぶ書きやすかった内容かなと思います。
特に今までは2商品だけ比較することが多かったのですが、今回は3商品の比較だったので、自分なりに論点を作りやすい設定になっていたかなぁと思います。
来年以降受験される方は、きちんと過去問の所見問題も解けるように練習することで合格できる、ということが今年の問題で分かったかなと思います。
3-2.経済価値ベースの保険負債評価
問題
(2)経済価値ベースの保険負債評価について、次の(ア)~(ウ)の各問に答えなさい。(計25点)
(ア)経済価値ベースの保険負債評価の概要について、現行の法定会計における責任準備金評価との相違を踏まえて簡潔に説明しなさい。(解答の制限字数は1000字)(5点)(イ)保険負債の評価前提に関し、「死亡率前提の上昇」「解約率前提の上昇」が経済価値ベースの保険負債評価額に与える影響を、逆ざや状態の平準払終身保険契約の評価を題材に、それぞれ簡潔に説明しなさい。(解答の制限字数はそれぞれ300字)(4点)
(ウ)あなたの会社では、経済価値ベースの保険負債評価を内部管理として経営に活用することを検討している。アクチュアリーとして留意すべき点について、活用目的を踏まえて所見を述べなさい。なお、解答にあたっては次の観点を含めること。(解答の制限字数は3500字)(16点)
A.経済価値ベースの保険負債評価の意義と留意点
B.非経済前提(死亡率や解約率等)の設定方法と留意点
C.前提条件・モデル・評価結果の妥当性向上、関係者の理解促進
※2025 年度末から適用が予定されている「経済価値ベースのソルベンシー規制」については説明する必要はない。
解答
(ア)経済価値ベースの保険負債評価の概要
(ア)
○経済価値ベースの保険負債評価の概要
- 経済価値ベースの保険負債とは、市場に含まれる情報と整合的に評価された負債である。ただし、保険契約は二次的なマーケットで取引されておらず、市場価格が存在しない。
- このため、経済価値ベースの保険負債は、保険契約の全ての権利と義務を反映した将来キャッシュ・フローの見積もりを用いた市場整合的な手法で評価する。
- 具体的には、保険事故発生率等の非経済前提は最良推計に基づき、経済前提は市場整合的に設定し、将来のキャッシュ・フローを展開し、評価日時点に割り戻すことで最良推計負債(キャッシュ・フローの期待現在価値)を算出する。
- 配当や動的解約、変額年金の最低保証コストといった損益の非対称性があるものは、確率論的シナリオ等を用いて適切にモデル化を行い、期待現在価値にそれら非対称性を反映させる。
- さらに、市場参加者が保険負債を引き受けることの対価として要求するであろうマージン(リスク調整)を算出し、最良推計負債(キャッシュ・フローの期待現在価値)に加算する。
- 加えて、契約時点の最良推計負債が負値となる場合、この負値の金額と0との差額は、一種のマージン(契約上のサービス・マージン)として負債計上することで、初期利益を繰延負債計上する。
- ○標準責任準備金制度と対比させた場合の特徴
- 標準責任準備金が平準純保険料式であり付加保険料や事業費支出を考慮しないのに対し、経済価値ベースの保険負債評価では付加保険料や事業費支出を含む、契約の履行に直接関連する全てのキャッシュ・フローを見積もることから、営業保険料式に相当するものと言える。
- 標準責任準備金がロックイン方式で契約期間を通じて同じ基礎率を使い続けるのに対し、経済価値ベースの保険負債評価では決算時点の最良推計や市場経済前提を用いることから、前提の変動により評価額が毎期大きく変動する。
- なお、標準責任準備金においても、基礎率がロックイン方式であることを補完する目的で、「保険業法第 121 条第 1 項第 1 号の確認に関する将来収支分析」(1 号収支分析)が導入されている。
- 標準責任準備金では特定の計算基礎率(標準利率、標準死亡率)を用いるのに対し、経済価値ベースの保険負債評価では評価日時点の見積もりを用いることから、各社の査定能力による死亡実績など経営努力を反映できる一方、会社間および会計期間間の会計数値の比較可能性が低下する可能性がある。
過去問H29から引用
https://www.actuaries.jp/lib/collection/books/H29/H29H.pdf
H29の問題文「標準責任準備金制度と対比させた場合の特徴」と完全に一緒ではないですが、模範解答に1号収支分析の話などもあるので、そのまま引用しました。
(イ)「死亡率前提の上昇」「解約率前提の上昇」が経済価値ベースの保険負債評価額に与える影響(逆ざや状態の平準払終身保険契約)
- 死亡率上昇に伴い、死亡給付の受給者が増加することで、経済価値ベースの保険負債評価額が増加方向に動き、また将来の収入保険料見込みも減少するので、経済価値ベースの保険負債評価額が増加方向に動くと考えられる。
- 一方、逆ざや(利差損がマイナス)状態であるので、死亡率が上昇することで、継続する契約者が減るので、経済価値ベースの保険負債評価額は減少することも考えられる。
- 解約率上昇に伴い、死亡給付の受給者が減少することで、経済価値ベースの保険負債評価額が減少方向に動き、一方、将来の収入保険料見込みも減少するので、経済価値ベースの保険負債評価額が増加方向に動くと考えられる。
- また、解約控除が収益へのインパクトが大きい商品であれば、解約率上昇に伴い、解約差損益が見込めるので、経済価値ベースの保険負債評価額が減少方向に動く場合もある。
- 逆ざや(利差損がマイナス)状態であるので、解約率が上昇することで、継続する契約者が減るので、経済価値ベースの保険負債評価額は減少することも考えられる。
(ウ)経済価値ベースの保険負債評価を内部管理への活用
(ウ)の所見部分については、筆者が必要と考える論点を列挙します。
- 現行の標準責任準備金制度をはじめとするロックイン方式のデメリットとして、次が考えられる。
- 金利低下局面等でのソルベンシーの確保:契約時の評価基礎率を使用し続けることから、利率低下局面では、契約時の高い利率を用いて責任準備金を少なめに評価することがあり、支払能力確保の面で問題となる場合がある。
- 金利上昇局面では、サープラスが過小となる場合がある:金利低下局面とは逆に、金利上昇局面では、債券を時価評価する場合、サープラスが過小に評価される欠点がある。
- 予定利率の設定方法:標準利率が足元の市場金利とマッチせずに低い水準となっている場合、保険料計算用の予定利率を直近の市場金利に合わせると、標準責任準備金積増が発生することがある。
- 標準基礎率の設定方法:仮に、業界共通の経験率の蓄積が乏しい商品に対して標準基礎率を設定しようとした場合、各社がロック・フリー方式の基礎率を設定するよりも困難な場合がある。
- 上記のロックイン方式のデメリットを補完する役割として、ロックフリー方式である経済価値ベースの保険負債評価を用いることが重要である。ロックフリー方式のメリットは次の通り。
- 資産評価と整合的:バランスシート全体を市場整合的なものとした場合、資産と負債の評価が整合的となる。
- 2025年度末にはじまる経済価値ベースのソルベンシー規制とも整合的
- ERMとも整合的
- 国際会計基準などの海外トレンドとも整合的
- 一方、経済価値ベースの保険負債評価には次のようなデメリットがあるので、留意が必要
- 利益が不安定:責任準備金評価基礎率の遡及変更は、責任準備金の大幅変更をもたらす場合、単年度の利益が不安定となる。
- 契約者配当が不安定:例えば、逆ざや契約等について責任準備金の変更額を積み増そうとする場合、当該保険群団の剰余だけでは不足するため、保険会社が過去蓄積してきた内部留保を充当せざるを得ず、当該保険群団以外の保険群団に配当還元の減少等の影響を及ぼし、契約間の衡平性を阻害することが考えられる。
- 実務負荷:フォーミュラ計算が可能なロック・イン方式とは異なり、実務負荷が大きい。
- 比較可能性:計算前提が金利環境等に大きく影響を受けることや、計算方法に比較的恣意性が生じるため、年度間や会社間の比較が難しい。
- 以上、経済価値ベースの保険負債評価はデメリットもあるものの、現状の日本の生命保険会計によるデメリット等を補完する役割をもっているので、会社の収益性を市場整合的に評価したり、将来の金利の変動に伴うソルベンシーの十分な確保、ERMの推進、IFRS17などの国際会計基準導入によるグローバル化の進展などを目的として、内部管理において、経営に活用できると考える。
- 保険事故発生率・事業費・継続率等の非経済前提は、過去・現在・将来を考慮した最良推定に基づき設定。
- 死亡率や医療給付率については、予定発生率に使われる性別・年齢のみの要素に限らず、経過年度別や契約チャネル別に設定を行う場合もある。
- 現在、上昇(下降)トレンドがある場合には、それが継続する見込みがあれば、それを織り込んで非経済前提を設定する。
- また、基本は会社の実績データを用いて、将来の最良推定を設定するが、実績データが少ないなどの理由でそれが困難な場合は、公的データや他社からデータを購入したり、データの補外を行うなど、分析が必要。
- 解約率については、実績データがあったとしても、会社の営業戦略やマーケティング戦略、風評リスクなどの影響を大きく受けやすいので、ただ数値を計算するだけでなく、その背後にある背景をきちんと確認すべきである。
- また、金利環境等に応じて変化する動的解約率の分析を行うことも有用である。
- 一方、実務負荷には留意が必要である。(過去問H29から引用)
- 経済価値ベースの保険負債評価においては、前提となる基礎率の設定や、将来キャッシュ・フローの見積もりなど、従来の決算よりも実務負荷の大きなものとなる。限られた決算スケジュールで対応可能となるよう、物的なインフラ(システム、データ)整備や人的な体制整備を行うとともに、実務対応可能な制度となるよう、制度内容そのものや、制度内容の決定プロセス(フィールド・テストやパブリック・コメントなどの実施)、導入までの準備期間などについて、必要に応じて会計制度設定主体に対する意見発信を行うことが考えられる。
- 経済価値ベースの保険負債評価の実務負荷軽減や計算効率向上のため、モデル・ポイントを使用した算出も許容されるであろう。ただし、当然ながら、保有契約全件を対象にして算出した額との差がどれくらいか、投資家向けという目的に応じた精度で計算されているかを検証する必要がある。
- また、前提によって結果が大きく変わることや、特定の前提を使用しない(評価日時点の見積もりを使用する)ことから、実務担当者の恣意性の介入が排除されているかといった前提の適切性を検証する体制も必要となる。この意味で、保険計理人の果たすべき役割についても重要性が増すと考えられる。さらに、モデルの検証体制を含むガバナンス体制の構築も必要だろう。
- 前提条件の妥当性向上
- 金利などの経済前提については、計算時点の最新の数値を前提として用いることが重要である。
- ただし、40年超など市場金利が存在しない年限については、終局金利をどう取り扱うかという論点もある。
- 上記でも述べたが、非経済前提については、チャネルや経過年度別など、様々な要因を加味したうえで、将来予測を行うことが重要である。
- 必要に応じては、機械学習などのデータサイエンスを用いて、分析することも必要である。ただし、結果の評価や計算過程が不明瞭になりやすいなど、デメリットもあるので、留意が必要。
- モデルの妥当性向上
- 従来の生命保険の責任準備金評価では、決定論的アプローチが多く用いられてきた。
- モデルの妥当性を向上させるために、確率論的アプローチを採用することも検討に値する。特に、変額保険等の最低保証のある商品においては、より確率論的アプローチがなじむと考えられる。
- また、死亡率モデル、解約率モデル、医療給付モデルなど、モデル化の対象を細分化することで、より妥当性を向上できると考えられる。
- 一方、複数のモデルを統合するときに、相関係数を0とするのか、といった論点が生じる。細分化すればするほどよいというわけではないことに留意が必要。
- 評価結果の妥当性向上
- 社内でのダブルチェック体制はもちろんのこと、変動要因分析などを行うことで、評価結果の妥当性を上げることが可能である。
- 保険計理人にも主体的に参画してもらうことが有用である。
- また外部のコンサルティング会社などに、チェックを依頼することでより評価結果の信頼性向上が期待できる。
- 関係者の理解促進
- 経済価値ベースの保険負債評価は高度な内容なので、経営陣への啓発が必要である。
- 株主などの外部へ開示するためには、より説明責任が求められる。
- よりアクチュアリーの説明能力が求められる。
- 最新動向にキャッチアップするために、アクチュアリーの自己研鑽も求められる。
解説
(ア)経済価値ベースの保険負債評価の概要
過去問にも出たことがある内容なので、しっかりと過去問を勉強しておけば、点数が取れた内容だと思います。
(イ)「死亡率前提の上昇」「解約率前提の上昇」が経済価値ベースの保険負債評価額に与える影響(逆ざや状態の平準払終身保険契約)
過去問でも、「解約実績が増加した場合の当期の「当期純利益(純剰余)」 およびEmbedded Valueのうちの「保有契約価値」に与える主な影響」(H21)などが出ていたので、それと同じような考え方で解けたかなと思います。
また、「逆ざや状態」が肝かもしれないですね。逆ざやというと、利差損なだけで、全体として収益がマイナスという言葉ではないと思います。しかし、全体としてマイナスという風にとらえてしまった受験生がいたかもしれません。(個人的には、わざわざ利差損といわず、逆ざやと記載されているので、そう捉えてしまっても問題ない気もしますが、どうなんでしょうか。)
(ウ)経済価値ベースの保険負債評価を内部管理への活用
過去にも「ロックフリー方式の保険負債評価」の所見は出ているので、過去問をちゃんと勉強をしていれば解けたかなという印象です。
一方、「前提条件(非経済前提や経済前提)・モデル・評価結果の妥当性向上」にフォーカスをあてた問題はなかった気がするので、いかに自分の頭で考えて書けたかどうかが重要だと思います。(私の回答は稚拙かもしれないので、忌憚なきご意見をコメント欄でお願いいたします!こういった論点もあるよ的なことも教えてください!)
私は2025年に導入される「経済価値ベースのソルベンシー規制」まで、経済価値ベース周りは出ないかなと思っていました。ただ、他の分野を見渡しても出せる内容は少ないので、妥当な出題かなと思っております。来年の問題では、「経済価値ベースのソルベンシー規制」をマークしておくべきですし、そろそろ「リスク管理」からも出るかなぁと予想しております。
一言
最後までご覧いただきありがとうございました。
生保2全体として言えることは、今年は特には過去問からの出題が多かった印象です。なので、ちゃんと勉強していれば点が取れた問題が多かったのではないでしょうか。
そういえば、『リスク管理』からの出題がなかったですね。教科書の記載が難解なので、苦労して暗記した人は多かったと思います。ちゃんと覚えた方は、少し寂しいですかね(笑)
試験指導を行っている身としては、アクチュアリー育成塾の試験対策の暗記集を覚えておけば、十分に合格点が取れる内容だったので、一安心でした。
今回点がとれなかった人は、改めて勉強をしましょう。
もし、「自分で勉強を継続するのが苦手」「なにを覚えたらよいかわからない」という人は、アクチュアリー育成塾の試験対策を覗いてみてください。弊塾では、オリジナルの暗記集の暗記を徹底して行うので、合格に最短・最速で近づくことができます。
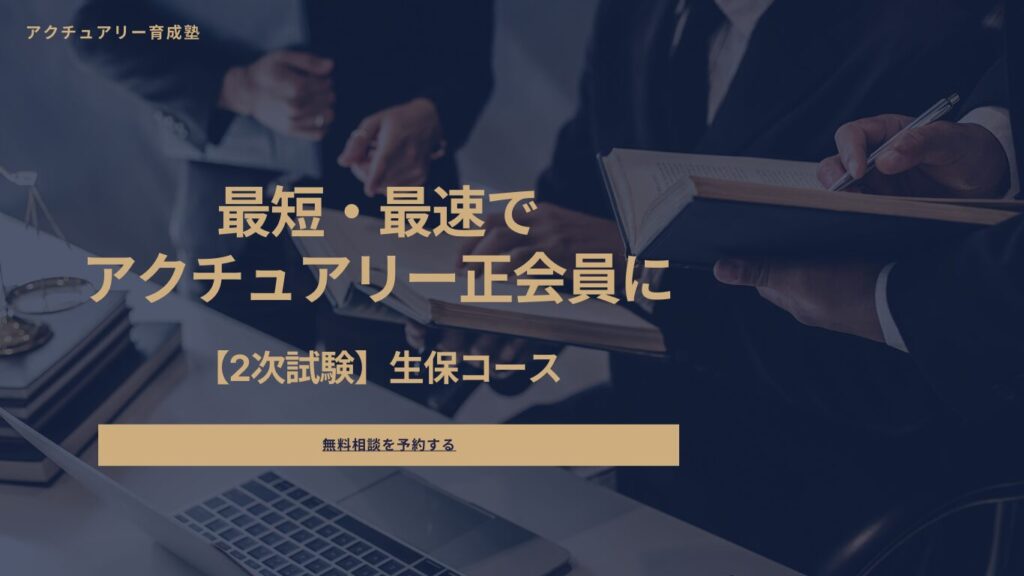

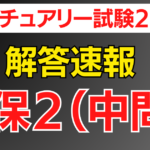
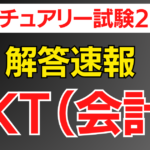
コメント