アクチュアリー2次試験はなぜ難しいのか?
アクチュアリーの2次試験は、単なる知識の暗記や公式の理解だけでは突破が難しい試験です。一次試験を突破した方であっても、2次試験では「論述力」や「所見力」といった、より高度なアウトプットが求められます。
一次試験との違い
一次試験では、数理的な計算能力が主に問われます。しかし、2次試験では、与えられた状況や設問に対して、自分の言葉で意見や所見を論理的に表現する力が求められます。
「論述力」と「所見力」が問われる試験
単に「正しい答え」を出すだけでなく、「なぜそう考えたのか」「どんな背景があるのか」といった、自分なりの視点と説得力が試されるのがアクチュアリー2次試験です。だからこそ、普段からの思考力・問題意識・仮説構築が合否を分けます。
思考のコツ①:問題意識を持つ習慣を身につけよう
「なぜ?」を放置しない姿勢が論点力につながる
2次試験で高評価を得る答案には、単なる知識ではなく「視点」や「論点」があります。日常生活や実務の中で「なぜこうなっているのだろう?」と疑問に思ったことを深掘りする習慣が、自然と良い所見を書くことにつながります。
たとえば、金利環境が変化したときに「各社の商品設計がどう変わるのか?」「その背景にはどんな経済要因があるのか?」と考えてみることが重要です。
疑問に感じたことはメモしてストック
疑問はその場でメモし、時間があるときに深掘りするようにしましょう。スマホのメモアプリやノートを活用し、後から自分の思考を振り返れるようにすることも有効です。これが「問題意識を持つ力」のトレーニングになります。
思考のコツ②:仮説→調査→検証の流れで理解を深める
仮説思考が答案の説得力を高める理由
「なぜそうなるのか?」と感じたとき、自分なりの仮説をまず立ててみる。次に、その仮説を裏付けるために調べ、検証する。このプロセスを繰り返すことで、思考の筋道が明確になり、答案の説得力が格段に上がります。
例えば、「経済価値ベースのソルベンシー規制が導入されると、保険会社の経営はどう変わるか?」という問いに対し、自分の仮説をもって調べてみる。そして、正会員の先輩や試験勉強中の同僚等と議論をする。普段からこうした訓練を積んでおくと、2次試験の所見がすらすら書けるようになります。
活用したい情報源:金融庁・各社プレスリリース・論文など
情報収集は信頼性が命です。市販の書籍、金融庁の公開資料、各保険会社のプレスリリース、日本アクチュアリー会の論文などを積極的に活用して、知識をストックしましょう。新聞や業界誌もリアルタイムな話題に触れられるため有益です。
思考のコツ③:実務や社会とのつながりを意識しよう
机上の空論で終わらせない学び方
試験勉強というと、どうしても抽象的な理論に終始しがちです。しかし、2次試験では「現実との接点」が問われる場面も多くあります。だからこそ、「この制度変更が実務にどう影響するか?」という視点で学ぶことが大切です。
具体的な事例から視点を広げるトレーニング
たとえば「なぜ株式会社なのに有配当契約を取り扱っているのか?」という問いに対して、その背後にある歴史的経緯や制度的理由を探ることは、視点の拡張につながります。こうした実務的観点を意識することで、所見に深みが出ます。
まとめ:日常の疑問がアクチュアリー2次試験の突破力になる
勉強を楽しく、実りあるものにするために
アクチュアリー2次試験は「知識量」だけでなく「考える力」「伝える力」が問われる試験です。問題意識を持ち、自分なりの仮説を立て、調べることで、思考の深みとアウトプット力が養われます。
暗記型の勉強がつまらないと感じたら、「これは実務にどう関係するのか?」と問いかけてみてください。きっと勉強が楽しくなり、合格にも近づくはずです。
これらの思考法は一朝一夕で身につくのではありません。常に意識しながら勉強することで身に付き・役に立つものです。この思考法は正会員になった後も役に立ちますので、試験まで頑張っていきましょう。
無料相談・講座情報はこちら
当塾では、アクチュアリー2次試験に向けた個別指導サービスを提供しています。生保2次については暗記集も渡しているので、最短最速で合格するために効率的に勉強できます。具体的な勉強の進め方に悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
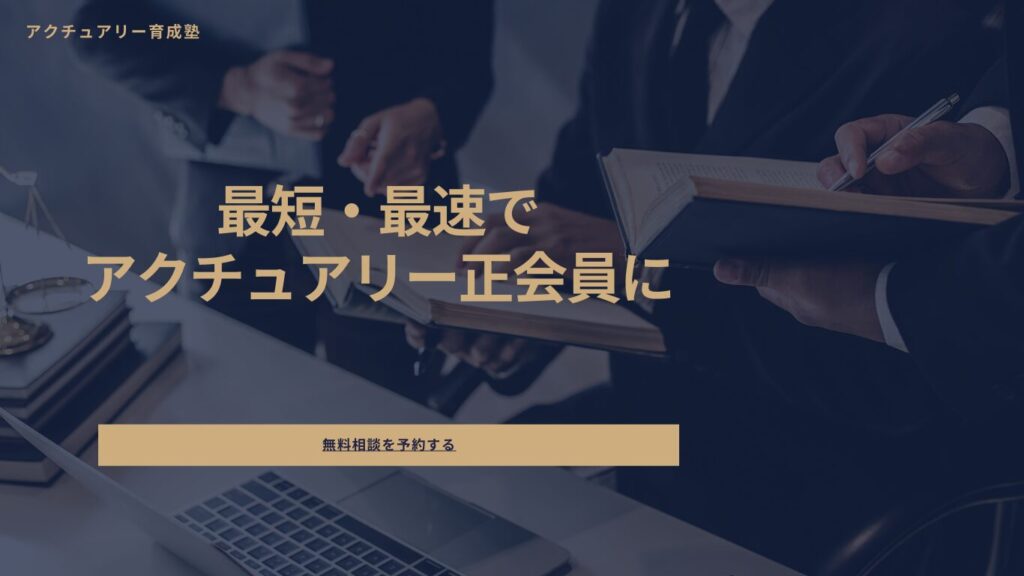
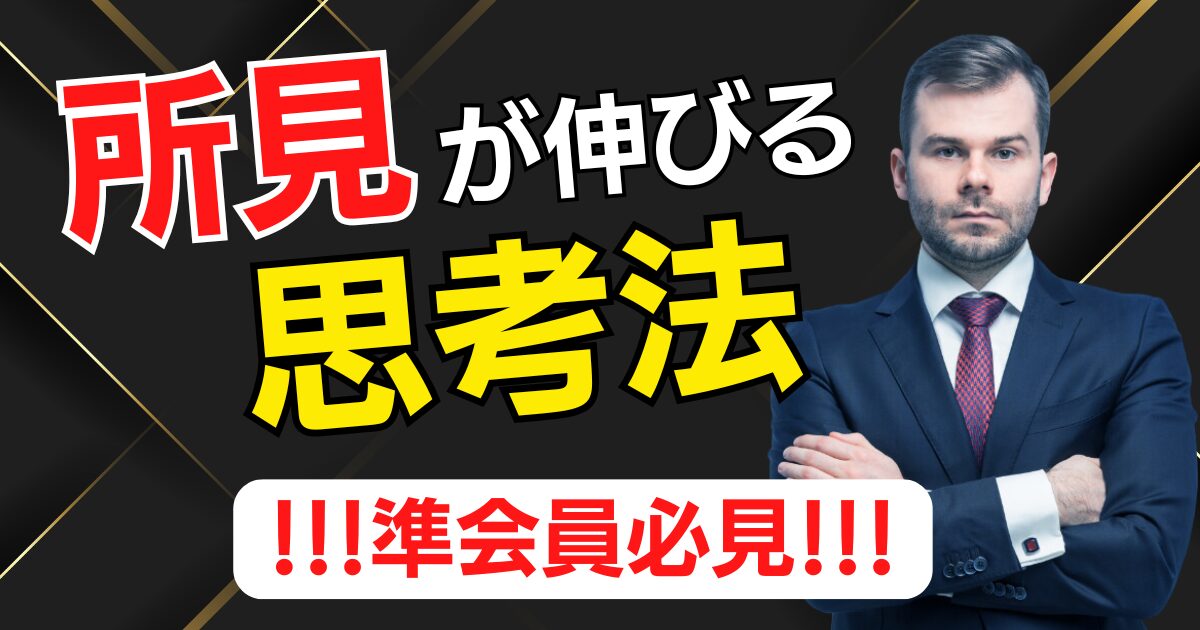

コメント