
2024年度の生保1大問の試験問題を解説します。
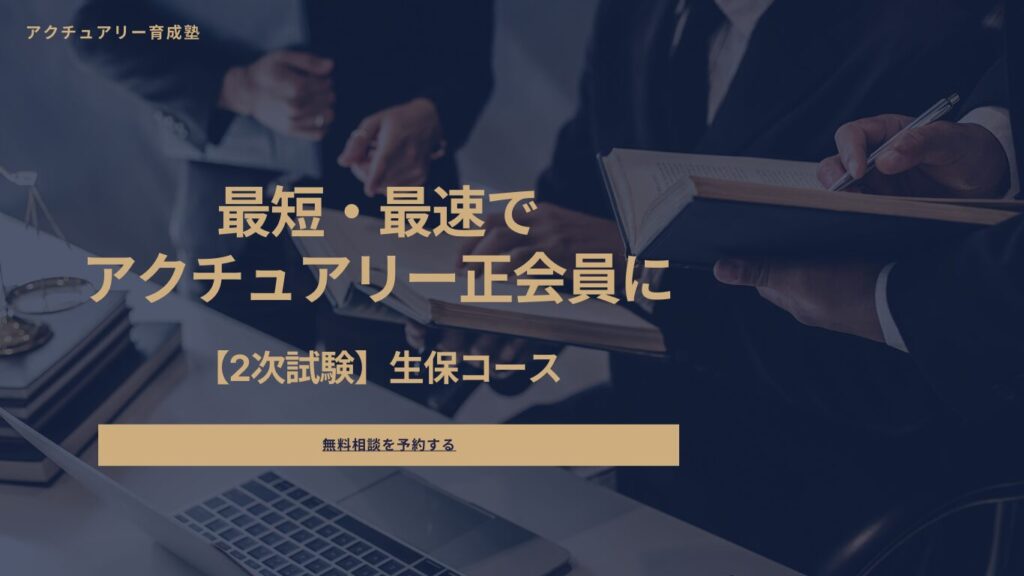
※本解答速報は、試験問題に対する参考解答を提供するものであり、公式解答ではありません。正確な解答は、日本アクチュアリー会が発表する公式情報をご確認ください。
本情報の作成には細心の注意を払っておりますが、誤りが含まれる可能性があります。本速報を利用することで生じるいかなる結果についても、当方は責任を負いかねます。
間違えている箇所がございましたら、コメントでご教示いただけますと幸いです。
問題については、日本アクチュアリー会のサイトから引用させていただいております。
https://www.actuaries.jp/examin/2024exam/20241213/2024-G-1213.pdf
解答作成にあたっては、ある方にご協力いただきました。(匿名希望でしたので、名前は公表いたしません。)
3-1.積立保険の開発
問題
問題3.次の(1)、(2)の各問に答えなさい。(50点)
(1)次の(ア)~(ウ)の各問に答えなさい。(25点)
(ア)予定事業費の設定に際して留意すべき点として、「十分性」および「普遍性・公平性」について説明しなさい。(200字程度)(2点)(イ)件数比例および責任準備金比例の予定事業費体系について、「費用主義と効用主義」の観点から説明しなさい。(400字程度)(4点)
(ウ)あなたの会社では、現在、営業職員チャネルで長期の保障性商品を中心に販売している。昨今の環境変化を踏まえ、新たに若齢層をターゲットとして「短期間で満期となる平準払積立保険」を開発することを検討している。
【環境変化】
・晩婚化・少子化等により、主に若年齢層において保障性商品に対するニーズが変化している。
・政府による資産形成にかかる税制優遇制度の導入により、消費者の資産運用に対する関心が高まっている。
・市場金利や物価は上昇傾向にある。
商品開発を行うにあたり、アクチュアリーとして留意すべき点を説明し、所見を述べなさい。
なお、解答にあたっては、以下の観点を含めること。(3500字程度)(19点)【観点】
・開発する目的
・保険給付等の詳細設計
・販売政策
・実際にかかる事業費と具体的な予定事業費体系の例示およびその考え方
・本商品の収益性
解答
(ア)予定事業費の設定に際して留意すべき点
(ア)
- 十分性
・一定の保険群団の中においてその群団から入る保険料中の予定事業費をもってその群団の運営に必要な事業費の全てを原則として賄う必要がある。
・この十分性が満たされないような場合、他の群団との公平性の問題が生ずる。
- 普遍性、公平性
・一つの方式でどれだけ多くの保険種類を矛盾なくまとめられるかという普遍性の問題とその一つの方式の中での保険種類間の公平性の問題がある。
・両者はトレードオフの関係にあることからその調和に留意する。
(イ)件数比例および責任準備金比例の予定事業費体系
(イ)
- 実態として保険金や保険料の大きさに比例しないいずれの契約にも概ね同程度生じる事業費がある。
- このような事業費に対応する予定事業費を設定する場合、1件あたり予定事業費を定め、これをこの部分以外の保険金あたりの営業保険料率に保険金額を乗じたものに加算し最終的な営業保険料とする方式が考えられる。
- これにより予定事業費を実際にかかる事業費の型と大きさで賦課しようとする費用主義を満たすことができる。
- 効用主義の観点からは保険商品の効用は「保障効用」と「貯蓄効用」にわけられる。
- 投資信託など他業界の貯蓄効用を期待した資産運用商品では投資金額に比例して経費が控除されているとおり「貯蓄効用」に対応するのは責任準備金比例の予定事業費体系である方が顧客の納得感を得やすく運用利回り表示などとも 親和性が高い。
- これにより保険商品の提供する効用に比例した予定事業費を課すことができ効用主義を満たすことができる。
(ウ)積立保険の開発
(ウ)の所見部分については、筆者が必要と考える論点を列挙します。
- 人口動態の変化による既存マーケットの飽和、縮小
- 事業規模の縮小は最終的には契約者利益を損なう
- 環境変化に対して商品の市場競争力を確保
- 従来の保障性商品に加えて貯蓄性商品をポートフォリオとして持つことでリスク分散
- 当該商品を動線に若齢層にリーチすることでライフステージに応じた自社との中長期的な関係構築を図る
- 途中給付は既払いPを返還とすることで保障要素を薄くし貯蓄性としての魅力を高める
- 保障は薄い災害保障とすることで発生率を簡易的に一律にしコスト低減、合わせて無選択も検討しさらなるコスト低減を図る
- 解約時に解約控除を大きくとると商品魅力の低下につながるためインターネットチャネルを利用して新契約費を抑える、又はV比例とすることで解約水準の引き上げを図る 困難な場合は再加入に制限を設ける、解約動向をモニタリングして販売後機動的な調整を図る
- 貯蓄性商品のニーズが高いと見込まれる銀行窓販チャネルを検討
- ただし手数料水準が高くつきやすいためL字型にするなど工夫、当該チャネルでセルフサポートできているか注意
- 銀行窓販チャネルでは説明負荷の観点から簡素な商品体系の方が好ましい
- 保険給付等の詳細設計で述べた解約動向に応じて機動的な調整を図る場合には販売当初の販売量を制限しデータが蓄積してきた段階で本格展開することも検討
- 解約控除を抑える観点からV比例が望ましい、ただし販売側のインセンティブ減少に注意
- システム開発等にかかる初期コストを今回の販売からどの程度回収するか、中長期的に当該商品を主力化していく方針があればその見込みを反映、件数比例で賦課すると保険料の小さい契約の付加保険料占有率か過大となる恐れもあるため公平性の観点からS比例を検討
- 金利上昇:平準払いは一般に順ざやとなる、保守的に決定する観点からは上昇を見越して過度に高い水準としない、金利上昇に伴うP水準引き下げはP比例予定事業費収入の減少効果もある、標準Vの積み増し負担に注意
- インフレ:保険金額を引き上げた場合にはSやP比例の予定事業費収入の増加効果もある、費差損益の圧迫要因となる、家計圧迫による解約動向に注意
- 貯蓄性を重視し保障要素を薄くした場合損益の主な源泉は利差損益となり死差損益は薄い
- 短期で満期になることから不確実性は相対的に低いとして安全割増を薄くのせる場合さらに損益は薄くなる
- 他の投資商品の動向を受けやすい:モニタリング、機動的な販売政策の変更
- 税制の変化の影響を受けやすい:長期的な視点をもった商品開発
- 銀行窓販の場合収益ボラティリティが大きい:販売量の予測は慎重に
解説
(ア)(イ)
テキスト本文(1-14~17)からの記述出題。類似問題:H29-3-1-2 H20-4-1-1
内容としては、教科書および過去問に記載がある内容なので、問題ないかなと思います。
ここで9割以上とれるかどうかが合否を分けます。実際、ここで満点が取れれば6点なので、大問1題の40%を占めます。
合格するためには、所見も大切ですが、とにかく教科書・過去問の暗記が大切です!
(ウ)
「積立保険」の問題です。正直、積立保険という言葉は一般的ではない気がしますが、「短期間で満期となる平準払」と記載があるので、貯蓄性商品を連想できるかなと思います。一方、損保数理でも積立保険という用語が出てくるので、それと混同する人もいたかもしれません。
実務経験がある身からすると、「ただの平準払貯蓄性商品ね」となるのですが、受験生はどう考えて記述したのでしょうか。
もし今後、定義があいまいな問題が出たら、自分の思う定義を最初に記述した方がいいと思います。その方が、知識の前提の一致が採点官と行うことができるので、採点の際の印象がよくなるかなと思います。
商品開発の経験がある人と話をしている中で、明治安田生命の「じぶんの積立」という商品が題材なのではないかと話がでましたが、憶測の域は出ません。
一方、生保1の問題を解くうえでは、業界の商品ラインナップをある程度見ておいた方が、所見を書くうえで有用です。松岡のXやLinkedInで「保険業界ニュース」として新商品情報を定期的にアップしていますので、受験生の方はフォローお願いします!(笑)
3-2.がん診断一時金商品の開発
問題
(2)次の(ア)、(イ)の各問に答えなさい。(25点)
(ア)以下の①から④はそれぞれ、商品開発において将来にわたる収支の変動を制御する方法である。
それぞれの収支の変動を制御する仕組みを、簡潔に説明しなさい。(各150字以内。なお、制限字数は解答字数の上限であって目安ではない。)(4点)
①商品設計
②契約群団のコントロール
③商品ポートフォリオ
④事後モニタリングと改善アクション(イ)あなたの会社では、がんを保障する商品として、がんと診断された場合に一時金を給付する商品を提供している。当商品に関して、あなたの会社では、医療技術の向上等により以下のような将来的な環境変化を見込んでいる。
【将来の環境変化】
・顧客が「自身のがんの罹患リスク」を高い精度で自ら推定できる技術の普及
・診断技術の向上等によるがんの早期発見の増加
・がんの完治・寛解者の増加や、がんの治療方法の多様化これらの環境変化が当商品へ及ぼす影響について懸念の声が上がっており、改めて当状況について検討が必要となっている。これらの環境変化を見据えて、どのようなモニタリングを行うか、また、考えられる対応策とそれを採用する際の留意点について、アクチュアリーとして所見を述べなさい。なお、解答にあたっては、以下の観点を含めること。(3500字程度)(21点)
【観点】
・環境変化が当商品に及ぼす影響
・環境変化を見据えた事後モニタリング(具体的な内容とその目的含む)
・商品改定や料率改定
・販売政策の変更
・その他の対応策
解答
(ア)収支の変動を制御する仕組み
(ア)
①商品設計
・保険期間を10年程度と比較的短期に設定し、保険期間終了後に改めて同じ保険で更新する更新型保険とすることで更新のタイミングで新たな計算基礎率に基づく営業保険料を適用することができるので当初定めた営業保険料を適用する保険期間が限定でき、将来の不確実性に備えることができる。
・生存保障と死亡保障を組み合わせる(養老保険など)②契約群団のコントロール
・更新の際に改めて危険選択を行う場合は更新後の契約群団の保険引受リスク量をコントロールできることになるが更新の際に被保険者の健康状態に応じて 割増保険料の適用や謝絶することが許容されるのかに留意する必要がある。
・一方更新の際に危険選択を行わない場合は事業費がさらに低廉となるがリスク濃縮に留意する。③商品ポートフォリオ
・生存保障の商品と死亡保障の商品を併売する
・複数の医療給付の特約を作成し、セットで販売を行う
④事後モニタリングと改善アクション
・商品開発時だけでなく販売後のモニタリング結果に応じて機動的に販売施策や価格を調整していくPDCAサイクルによって長期間にわたる商品事業の健全性をより強固にする。
・悪いことが起きた場合への対処という側面だけではなく将来の商品改善や新商品開発の素材として持続的成長といった意味でのPDCAにも活用され得る。
(イ)がん診断一時金商品
(イ)の所見部分については、筆者が必要と考える論点を列挙します。
- 逆選択の加入が増加し想定していた保険群団から乖離し発生率が悪化する
- 早期発見により今までより罹患の発生の検知が早まり、一時的に発生率が前倒しで悪化する
- 自社の発生率の動向を要因別、チャネル別、契約時期別、年齢群団別に分解する、その際コントロール可能、不可能な要因に分けコントロール不可能な要因はリスク許容度に応じてリスクテイクするか判断
- 業界のがんの発生動向と自社の動向を比較しモラルリスクや逆選択混入の兆候を読み取る
- 完治者の増加が見込まれ罹患歴のある人向けの商品ニーズの高まり
- 治療方法の多様化を受けて一時金ではなく治療期間、内容に応じた給付を検討
- 一時金はモラルリスクが高いため他の給付形態を検討
- モラルリスク対策として待ち期間を設ける、善意の第三者とのバランスも考慮
- 健康還付金を設けることでモラルリスクを軽減しながらリスク分散
- 販売時の査定方法の厳格化
- 発生率動向の不確実性が大きすぎる場合は販売中止も検討
- 販売量の制限、環境が落ち着いてきてから販売拡大
- 特定チャネルの実績が著しく悪化している場合にはチャネルの変更も検討
解説
(ア)収支の変動を制御する仕組み
①テキスト本文(1-21)からの記述出題
②テキスト本文(4-26)からの記述出題
③テキスト該当なし
④テキスト本文(4-5、4-22)からの記述出題
直接教科書の記載がない部分もありますが、第4章をちゃんと覚えていれば、考えながら書ける内容かなと思います。
(イ)がん診断一時金商品
がん保険に関しては逆選択やモラルリスク等、典型的な内容はすぐ思いつくが、がん保険固有の知識がないとそこからの深掘りが難しいため、実務経験がない人は書くのが難しかったかもしれません。
ただし、がんの早期発見などは、業界でのホットトピックなので、常に最新動向を追っている人は、それなりに所見は書けたかもしれません。特に、遺伝子情報によるがんの早期発見や、市販のがんリスク検査による逆選択の混入は、数年前からずっと議論されています。
受験生の方は、普段のニュースを何気なく読むのではなく、「このニュースが保険商品開発にどういう影響をもたらすか?」という視点で日経新聞などを読むと、良い思考のトレーニングになります。
度々宣伝ですが、松岡のXやLinkedInで、日経新聞などのニュースが保険業界に与える影響などをコメントしながら、情報共有しておりますので、受験生の方はフォローお願いします!(笑)
一言
最後までご覧いただきありがとうございました。
生保1全体として言えることは、初見問題が多かった印象です。しかし、教科書や過去問を通して、ちゃんと勉強して、本質的な理解ができていたら、合格点は取れたと思います。
今回点がとれなかった人は、改めて勉強をしましょう。
もし、「自分で勉強を継続するのが苦手」「なにを覚えたらよいかわからない」という人は、アクチュアリー育成塾の試験対策を覗いてみてください。弊塾では、オリジナルの暗記集の暗記を徹底して行うので、合格に最短・最速で近づくことができます。
アクチュアリー育成塾の試験対策では、ただの丸暗記ではなく、業界の最新動向を踏まえた試験対策を行っています。
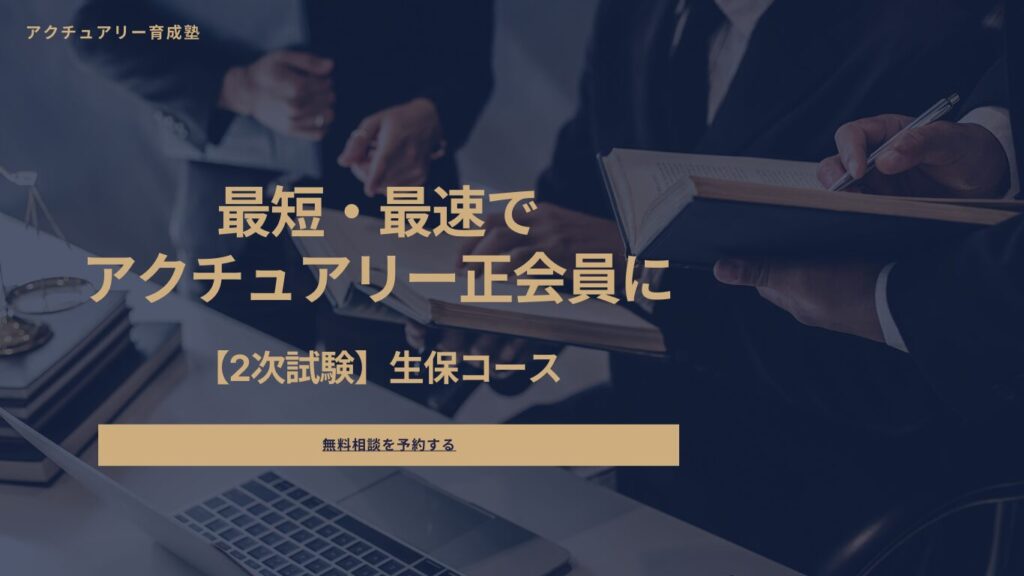
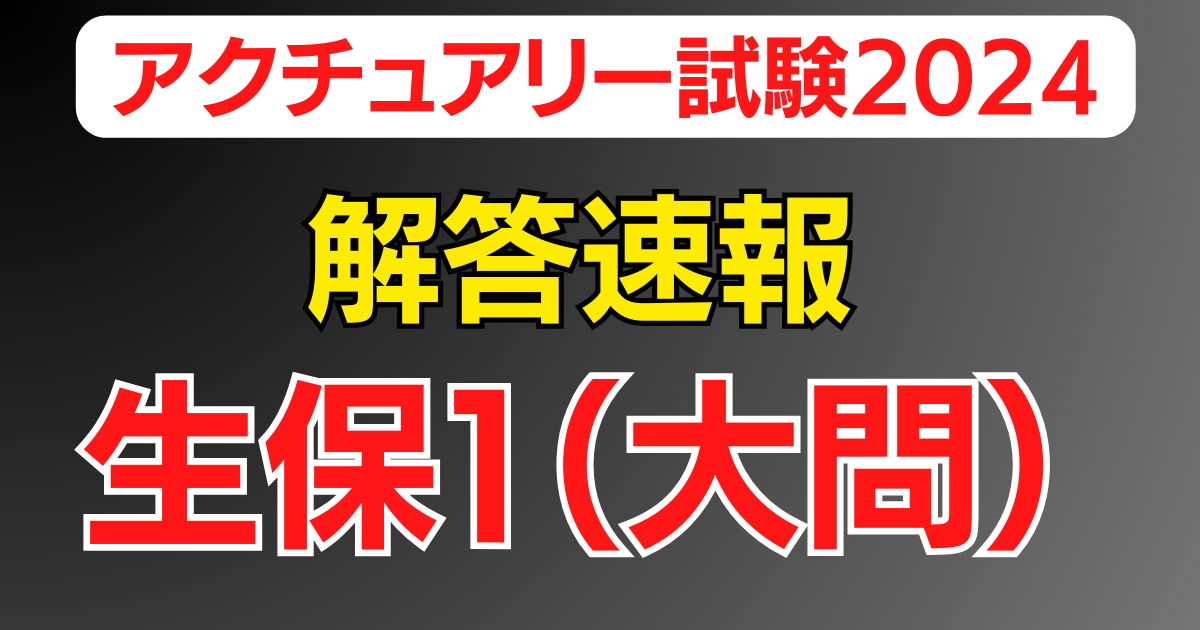
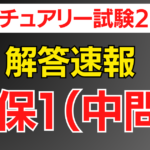

コメント