
2021年度の生保1大問の試験問題を解説します。
問題と解答については、日本アクチュアリー会のサイトから引用させていただいております。
https://www.actuaries.jp/lib/collection/books/2021/2021G.pdf
3-1.認知症保険の開発
問題
(1)次の①、②の各問に答えなさい。
① 第三分野商品の開発時において、予定発生率作成に用いる基礎データとして、自社データを用いる場合と公共データを用いる場合がある。それぞれのメリット・デメリットを簡潔に説明しなさい。(4点)
② あなたの会社では、人生100年時代・超高齢社会の到来を踏まえ、シニア向けの保障を充実させる観点から、新たに「認知症保険(※)」の開発を検討している。本商品の開発にあたり、商品設計、基礎率設定および本商品の導入に伴うリスクとそのリスク管理手法に関して、アクチュアリーとして留意すべき点を説明し、所見を述べなさい。(21点)
(※)
・責任開始前を含めて初めて「器質性認知症(症状や疾患が臓器・組織の形態的異常にもとづいて生じている認知症)」と診断確定された時に認知症保険金を支払い、保険契約は消滅する。
・あなたの会社では、給付事由を公的介護保険制度に連動させた介護保険において、認知症
を原因とした給付実績はあるものの、認知症保障の単独引受は本商品が初となる。
・保険料払込は有期払込とし、保険期間は終身とする。
・保険料払込期間中の死亡保険金・高度障害保険金・解約返戻金はないものとする。
解答
①自社データ・公共データのメリデメ
①
<自社データのメリット(○)、デメリット(×)>
○過去にも同様の保障内容の商品を販売していた場合、自社の査定方法、選択効果、販売チャネル等、個社の状況に基づいた分析を行うことができる。
○公共データに比べて、男女別・年齢別・経過年数別など詳細なデータを取得できる場合が多い。
×一般的に公共データよりデータ量(母数)が少なく、分析に十分な信頼性が得られない可能性がある。特に定常状態の集団になっていない場合、そのまま用いると過小評価となる。
×過去に類似の商品がない場合は、自社データの使用は困難である。
×基礎データに逆選択(モラルリスク)の影響を与える可能性がある。<公共データのメリット(○)、デメリット(×)>
○データ量(母数)が多い。基礎データに与える逆選択(モラルリスク)の影響は小さいと考えられる。
○過去未販売の新たな支払事由等、自社データに比べて、幅広いデータを取得できる。
×開発商品の支払事由に完全に適合するデータがない場合があり、使用目的に沿った補整が必要となる。
×選択効果の反映、また自社独自の査定を行っている場合はそれを反映するかどうかを検討する必要がある。
②所見
②の所見部分については、過去問の解答も参考にしつつ、筆者が必要と考える論点を追加して列挙します。
所見は「書き始める前に論点をまず書き出す。その後論点を肉付けしていく」方法をお勧めしています。そのうち、所見の書き方も記事にしますので、お楽しみに。
- 診査手法
- 簡易告知か健康診断結果の提出等を求めるか
- 不担保期間・初期給付の削減
- モラルリスクや診査手法の観点から設定
- 保険金額下限
- 必要保障額等の観点から設定
- 保険金額上限
- モラルリスクや保険料水準から設定
- 反対給付
- リスク管理の視点から導入。保険料の高料化に注意
- 加入年齢
- ニーズや公的保険制度に留意して設定
- 保険期間
- ニーズに備えて設定。介護は終身ニーズが高いか
- 払込期間
- 年金受給者になったあとにも払ってもらうか。ALMリスクなどにも留意
- 配当方式
- ニューリスクのため、保守的に設定
- 払込満了後の死亡保険金・解約返戻金
- 契約者保護の視点から設定
- 付帯サービス
- 認知症予防のためのサービスの提供可否
- 販売チャネル
- 営業職員チャネルかネットチャネルかで売り方や契約者属性が変わる
- 予定発生率
- 自社データ・公的データ
- 将来トレンド
- 予定死亡率
- 第3分野標準生命表を使用
- 予定事業費率
- 保険期間の長さに留意してインフレ考慮
- 開発コストや予想販売件数により設定
- 付帯サービスのコストについても留意
- 予定利率
- 一般勘定の予定利率を採用
- 再投資リスク等に留意
- 予定解約率
- 保守的に低く設定
- 監督指針に則る
- 引受リスク
- 発生率の不確実性
- モラルリスク
- 医療技術の変化
- 公的介護保険制度の変更
- 金利リスク
- 金利低下リスク
- 金利上昇リスク
- 収益検証
- P/Lインパクト。IFRS
- 損益分岐年等を考慮した資金繰りにも留意
- コミッションの水準に留意
- 再保険
- 引受リスクの移転
- 新契約費負担の軽減
- 責任準備金積増
- 責任準備金計算基礎率と保険料計算基礎率の乖離
- 第3分野ストレステストや負債十分性テスト
- 基礎率変更権行使
- 監督指針に則る
解説
「認知症保険の開発」の問題です
①自社データ・公共データのメリデメ
過去にも出ている問題なので、落としたくないですね
実際に予定発生率を作成する際にも、データの性質を考慮して加工をします。
したがって、この論点は実務でも役に立つのでしっかり覚えておきましょう。
ちなみに、プライシングをする際には、自社データや公共データ以外にも、データベンダー会社からデータを買うことがあります。
健康保険組合のデータを販売しているJMDC社(https://www.jmdc.co.jp/)は特に有名ですので、調べてみると面白いかもしれません
②認知症保険の開発
色んな会社で発売していますが、業界内の人間としては、あまり売れていないと聞くことが多いです
理由としては、定性的なものが多いですが、
- 認知症のニーズ喚起が難しい
- 認知症になったあとに保険金をもらっても自分で使えない場合があり、保険金受取人の指定がめんどう
- 販売に手間がかかるわりに手数料が低い(主力の医療保険を売った方が良い)
を聞くことが多いですね。まぁ、これはアクチュアリー的な視点ではなく、営業側の視点なので、所見でここまで書かなくてよいと思います。
しかし、販売件数(売れるか売れないか)は収益性、付加保険料水準、安全割増の設定に関わってくるので、実務としては重要です
3-2.一時払個人年金保険の販売再開
問題
(2)次の①、②の各問に答えなさい。
① 個人年金保険の代表的な年金支払種類を4つ挙げ、給付事由や給付金額の違いが分かるように、それぞれ簡潔に説明しなさい。ただし、年金支払の回数や通貨による違いは同一の年金支払種類であるものとする。(4点)
② あなたの会社では、わが国の昨今の超低金利環境を踏まえ、一時払個人年金保険の販売を停止していたが、下記の<外部環境の変化>を受けて、本商品の販売再開を検討している。
本商品の販売再開にあたり、商品設計、基礎率設定および販売再開に伴うリスクとそのリスク管理手法に関して、アクチュアリーとして留意すべき点を説明し、所見を述べなさい。なお、解答にあたっては、下記の<論点>について触れること。(21点)<外部環境の変化>
・わが国の金利水準は、今後、緩やかに上昇することが見込まれるが、急激に上昇することも
懸念される。
・人生100年時代の到来を踏まえた資産形成ニーズの高まりにより、本商品の魅力の向上が
期待される。
・競合他社は本商品と同様の商品の販売再開をした。<論点>
・安定的な商品供給
・将来の金利上昇に対する機動的な対応
・長寿リスクに対する顧客ニーズ
・競合他社に対する優位性の確保とそのための工夫
解答
①年金支払種類
①
※以下に年金支払種類ごとの解答例を記載。この他にも正しい記述が考えられるが、それらも含めた中から4つ挙げること。・確定年金:
(給付事由)年金の支払開始日から毎年、被保険者の生死に関わらず契約時に定めた一定期間、年金を支払う。
(給付金額)年金額は、年金支払期間により異なる。・終身年金:
(給付事由)年金の支払開始日から毎年、被保険者が生存している限り終身にわたり年金を支払う。
(給付金額)年金額は、被保険者の性・年齢により異なる。・有期年金:
(給付事由)年金の支払開始日から毎年、被保険者が生存している限り契約時に定めた一定期間、年金を支払う。
(給付金額)年金額は、年金支払期間の他、被保険者の性・年齢により異なる。同じ年金原資・年金支払期間の場合、死亡者分の持ち分が生存者に充てられるため確定年金よりも年金額が大きくなる。ただし、被保険者の死亡の時期により年金の受取総額は確定年金よりも少なくなることがある。・介護割増年金:
(給付事由)年金の支払開始後に被保険者が要介護状態となった場合、その状態が継続している間は、通常の年金に上乗せして割増年金を支払う。年金の支払開始前に確定年金や保証期間付終身年金からこの年金種類に変更されることが多い。
(給付金額)同じ年金原資額の場合、介護保障による割増分の支払があるため、介護割増年金で要介護状態でないときの年金額は介護割増が付かない年金に比べて小さくなる。・夫婦年金:
(給付事由)被保険者と配偶者のいずれかが生存している限り終身にわたり年金を支払う。
(給付金額)被保険者と配偶者のどちらか一方が死亡した場合でも年金額を減額しない夫婦年金の場合、被保険者が一人の終身年金と比較すると、夫婦年金の年金現価の方が大きくなるた
め、年金額は夫婦年金の方が小さくなる。
私が他に思いついたのは「変額年金」や「保証期間付終身年金」「逓増(逓減)年金」ですかね
変額年金:
(給付事由)年金の支払開始日から毎年、被保険者が生存かつ積立金額がある限り終身にわたり年金を支払う。
(給付金額)特別勘定の資産運用結果に応じて年金額が変動する。「定率取り崩し」「定額取り崩し」「定口数取り崩し」などが挙げられる
※これは、変額個人年金保険の場合の話です
②所見
②の所見部分については、過去問の解答も参考にしつつ、筆者が必要と考える論点を追加して列挙します。
- 診査手法
- 簡易告知か健康診断結果の提出等を求めるか
- 年金支払種類の工夫
- 契約者ニーズ、他社差別化
- 一時払保険料下限
- 収益性等の観点から設定
- トンチン性
- 契約者の理解
- 販売年齢(現行、「トンチン年金の場合、認可がとれているのは、40歳以上まで」)
- MVA
- 契約者理解
- 債券の売却損(益)リスクの移転が可能
- 利率変動型
- 将来的な金利上昇リスクに備える
- 再投資リスクの回避
- 予定利率の設定頻度
- 一時払いのため、毎月や月2回などの頻繁な設定が可能となる
- 有配当
- 契約者へのリスク転嫁
- 競争力の低下
- 保険期間の長期化
- 純イールドの場合、保険期間が長ければ、高い予定利率を設定できる
- デュレーションが長いと資産と負債のミスマッチが生じやすくなる
- 再投資リスクに留意
- 加入年齢
- ニーズや販売チャネルに応じて設定
- 保険期間
- ニーズに備えて設定
- 付帯サービス
- 健康増進サービスや相続サービス等の提供可否
- 販売チャネル
- 営業職員チャネルか窓販チャネルかで売り方や契約者属性が変わる
- 通貨
- 他国の金利環境等を鑑みながら、米ドル建商品などの開発も想定される
- 定額・変額
- 契約者ニーズや金利環境などを背景に、株式への投資を中心とした変額年金の開発も検討
- 予定死亡率
- 年金開始前と年金開始後で別の死亡率を使用
- 死亡率の改善トレンドなどを考慮
- 予定事業費率
- 保険期間の長さに留意してインフレ考慮
- 開発コストや予想販売件数により設定
- 年金開始後の生存確認コストや送金のコストに留意
- 予定利率
- 一時払のため、キャッシュフローマッチングに基づく、予定利率設定が考えられる
- 円建・米ドル建・豪ドル建の場合には、標準責任準備金の予定利率水準に留意する
- 社債等に投資する場合には、デフォルトリスクにも留意が必要
- 再投資リスク等に留意
- 予定利率設定タイミングと実際の運用タイミングのラグに注意
- 年金開始後の予定利率設定は年金開始時に行う
- タイムラグマージン
- MVAを導入する場合には、タイムラグマージンの水準に留意する
- 引受リスク
- 発生率の不確実性
- 長寿化のさらなる進展
- 医療技術の変化
- 金利リスク
- 金利低下リスク
- 金利上昇リスク
- 流動性リスク
- ストレステストの実施
- 動的解約による評価
- 安定的な商品供給
- 窓販チャネルなどの代理店を活用した販売の場合には、発売休止・再開の繰り返しはマーケットからの信用を損なうので、販売停止ラインについては留意が必要
- 収益検証
- P/Lインパクト、IFRS
- 損益分岐年等を考慮した資金繰りにも留意
- コミッションの水準に留意
- 再保険
- 引受リスクの移転
- 新契約費負担の軽減
- 責任準備金積増
- 責任準備金計算基礎率と保険料計算基礎率の乖離
解説
①年金支払種類
教科書に記載がないものなので、面をくらった受験生は多かったかもしれません
しかし、生保数理で「確定年金」「保証期間付終身年金」「終身年金」「逓増年金」など見たことあると思いますので、2,3個は思いつくのではないでしょうか
受験生は「教科書に載っていないものが出ても慌てない」ことを肝に銘じておきましょう
あなたが見たことない問題は、みんな見たことない問題です。
落ちついて考えて、思いつくことをしっかり書きましょう。
目新しい問題は、6~8割とれるように書くことを心がけましょう
②一時払個人年金保険の販売再開
通常、販売再開と言われれば、今まで販売停止中だったものを再開するだけなので、商品設計は変わらないのですが、題意をみると、「商品設計」も論点となるので、新商品開発と同様の論点を述べることが求められているのではないかと思います
過去問題でも「一時払外貨建保険」など一時払貯蓄性商品について出ているので、年金部分を加えて書けば、点は取れると思います
ちなみに、年金を支払うだけで、結構コストがかかるので、実務では「年1回支払」を採用している会社が多い印象です
毎月の年金支払は私個人は見たことがないです。最小でも隔月(2月に1回)ですかね。
公的年金の支払は偶数月なので、それを踏まえて「奇数月に年金をもらいませんか?」という話法があったりします


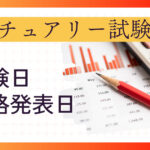
コメント